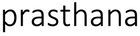inside of thought.#5 [デカダンスとグラマラス。ゴスから紐解くRick Owensの美的感覚。]
prasthana co., ltd. 代表/デザイナーの武井です。
10月。
色々と、やっと少し落ち着いてきました。
依然として9月に開催した、来季SS25展示会に纏わる諸業務はこれからもパラパラとありますが、それも10月末頃から順次、という感じ。
ちょっとだけ隙間が空きました。
現在、SS25サンプル一式は中国・上海にあります。
10月2週目のタイミング、上海はファッションウィークということで、有り難いご縁が繋がり現地ショールームに出展しているわけです。
今回はスケジュール諸々勘案して僕自身は現地には行かず、ショールームの方々にお任せする形を取りましたが、今後継続していけるようでしたら上海、是非行きたいもんです。
そんな感じで、精神的にも時間的にも少しの余裕ができましたので、超久しぶりのあれ、書いてみようかと思います。
「inside of thought.=思考の内側」と題した当記事は、このJOURNALコンテンツにおける所謂雑記的な位置付けとしていて、もう完全なる不定期更新、内容になんの制約もない自由気ままなもの。
今回はその#5、前回の#4はいつのことだったか、、あぁそうだ、BAUHAUSのことを書いたので去年の11月頃ですね、もうそろそろ1年も前のことになります。
日々のprasthana及びprasthana sendagaya storeの運営に関わること以外の題材、その時々で僕が書きたい内容を、一方的に皆さんに押し付けるというフォーマット。
ちょっと前の頭痛の話の際に、先生は頭痛い患者に対して脚や仙骨やお腹を触ったりする、と書きました。
これは、「身体は一つであり、様々な箇所同士が相互に密接に関連している」ということから。
この「inside of thought.」という記事の存在理由もそこにあります。
要するに、テーマは直接的な衣服に関することではなくても、思考は表現に密接に関連している。はず。
なんとなく雑学ひとつ増えるかも、くらいの気持ちで読み進めて頂くとちょうど良いかもしれません。
さて、そんな感じで表題にもありますが、今回は「デカダンスとグラマラス」について拙いながら所見を綴ってみようかと思います。
デカダンス=DECADANCE=退廃的
グラマラス=GLAMOROUS=魅惑的な、とか妖艶な、とか
この二つの要素を内包したスタイルを標榜しているブランドとして、僕が真っ先にイメージするのが「Rick Owens」です。

Rickはですね、僕が長いこと憧憬の念を持って見つめているブランドの一つでして、prasthanaとしての表現にも少なくない影響を受けています。
意識的にその存在を捉えたのは、僕が某セレクトショップで販売員としてのキャリアをスタートして間も無くの頃、そのショップで取扱のあった某ブランドのデザイナーさんが店頭にいらした際に「Rick Owens」を着用されていて「なんだこのバランス、!」と唸ったのが最初でした。
その方は、今や超大定番とされているスタイルを形成する、サルエルパンツとGEO BASKETを軸にスタイリングを組まれていたのですが、僕の圧倒的な知識不足で「BLAZER SBの亜種かなにか???」みたいな印象を持ったことを昨日のことのように思い出します。(改めて画像を見ると全く違う、、)

それから10年余りの時間の中、何度か転職&様々経験を積んで独立を決意、prasthana co., ltd.設立に至るのですが、なんだかんだ常に気になる存在、一生懸命その動向を追いかける、ということこそしなくはなりましたが、自分の美的な感覚とか価値観を形成する重要なファクターとして「Rick Owens」というブランドは僕の中に存在し続けています。
匂い立つようなデカダンなアングラ臭を強烈に発散しながら、他方でセレブにも愛されるエレガントなその佇まいは、まさに「DECADANCE&GLAMOROUS」。
この辺の理解として、Rick本人は「David Bowie」からの影響を公言しているのでそこからの派生、あくまで僕の主観になりますが、70年代から80年代にかけて勃興したロックシーンにおける一大潮流、グラムロック〜ポストパンク〜ゴシックロックといった一連の流れとの美意識の共通点を見出さずにはいられませんし、このカルチャーの探求をして「Rick Ownes」の物作り、その美的感覚の一端を紐解く鍵と成り得るのではないかと考えています。
70年代前半に世界的に大きな盛り上がりをみせたシーンであるグラムロックとは、バキバキのメイクとギラギラの煌びやかなステージ衣装に身を包み、なんなら演奏技術よりも世界観を重視する、と言い切ってしまっても良いのではないか、といった、音楽スタイルとしては非常にシンプルなロック。
それを、このジャンル特有の気怠い感じで歌い上げる、がデフォルトのスタイルです。

後に日本においては、この系譜はビジュアル系のムーブメントに繋がっていくわけなのですが、始祖は「T.Rex=Marc Bolan」とか「David Bowie(グラム期限定)」とか「Roxy Music」とか、になります。
「T.Rex」はあれですね、「20th Century Boy」という楽曲が、浦沢先生の「20世紀少年」でも主題として扱われていますから、耳馴染みのある方も多いことと思います。
そもそも語源がGLAMOROUSのGLAMですから、このグラムロックが体現していたスタイルって、兎に角煌びやかでいかがわしくてセクシーなイメージ。
この辺を題材にした映画作品なんかも、過去に沢山制作されているくらい、かなり鮮烈な印象を発散するものでした。
ムーブメントって、熱を帯びれば帯びるほどその終焉は唐突に訪れるもので、70年代の中頃にはこのグラムロックというジャンル自体が急激に失速し、一気に過去のものとなってしまいます。
その後、少しの時間を経て、70年代後半にパンク/ポストパンク/ニューウェーブのシーンが誕生するわけなのですが、その頃、イギリスの「BAUHAUS」というバンドがデビューします。

ここ、混同されて大分理解の障壁となってしまいかねない部分なので言及しておきます。(実際僕自身、戸惑った過去があります。)
「BAUHAUS」って、僕がその影響を幾度も公言しているドイツの芸術運動/教育機関=「BAUHAUS」と同名なんですね。
というか、「BAUHAUS(芸術)」からバンド名を取っているんです。
なんなら活動初期は「BAUHAUS1919」という名を冠していたそうで、この1919は「BAUHAUS(芸術)」がドイツ・ワイマールに開校した年ですから、めっちゃ関連を疑う、というより寧ろ、もう完全に一致だろ、となるわけです。
なんですが、この「BAUHAUS(バンド)」と「BAUHAUS(芸術)」は、実は関係ない、と言うと語弊があるかもしれませんが、その想いは「BAUHAUS(バンド)」側からの一方通行的なもので、リスペクト故のネーミングとアートワークの使用でした。
こんなことがまかり通ってしまった背景には、「BAUHAUS(芸術)」初代校長のヴァルター・グロピウスの詰めの甘さがあったそうで、建築家/デザイナーとしては偉人中の偉人のグロピウスですが、「BAUHAUS」とそれに纏わるアートワーク関連の著作権を宙ぶらりんにしていた、と。
要は、誰でもなんの規制もなく「BAUHAUS」を名乗ることができたわけです。
今の感覚では到底考えられないですが、そんな事情が背景にあったらしい。
こんな逸話も相まって、僕はグロピウスという人物にやたら興味を惹かれるんですよね。
遺された氏の言葉などからも、なんというか、いかにも直情的且つロマンティシズム溢れる人物だったのだろうな、と想像しています。
「人の心とは傘のようなものだ。開いた時に最も機能する。」
とても好きな言葉です。
話は脱線しましたが、その「BAUHAUS(バンド)」。
彼らは過ぎ去りしムーブメントであったグラムロック時代の名曲、「T.Rex / Telegram Sam」と「David Bowie / Ziggy Stardust」をカバーし、グラムロックの新たなる継承者として、その存在感を確立します。
シアトリカルなステージングや視覚的パフォーマンスが、音楽性と同様に高く評価をされ続けていて、活動を通じてバンドが醸し出していた世界感から、所謂ゴシックロックの先駆として、今に至るまでリスペクトを集め続けています。
グラムとかゴスとか単語が多くて「なんだこの文章、読み進めるのだるいな」と思われているかもしれませんが、否、いつも読んで頂いている方には少なからず響いているものと勝手に仮定して話を続けます。
その「BAUHAUS(バンド)」が体現したゴシックロック=ゴスですが、言葉で表現すると、ダークでモノクロの世界観を表現した、重く時にエキセントリックな側面も持ち合わせたロックの一ジャンル、というニュアンスになるかと思います。
あんまりこの辺に興味関心が無い方でも、実はわりと身近にその存在の片鱗があったりするもので、ゴスのBIG4だったか、そんな感じで評価されているバンドに「JOY DIVISION」がいますが、彼らの1st Fullである「Unknown Pleasures」はその音楽的価値/内容もさることながら、ジャケットのアートワークも超有名で、様々なところで使われまくっています。
最近だとユニクロかGUか忘れましたが、プリントTシャツをリリースしていたのは記憶に新しいと思います。

「BAUHAUS(バンド)」や「JOY DIVISION」、加えて「SIOUXSIE AND THE BANSHEES」、「THE CURE」などといったゴシックロックの礎を築いたレジェンドバンド群によるシーンの黎明期を経た80年代の初頭、ロンドンに「BAT CAVE」という伝説的なクラブがありました。
この「BAT CAVE」はゴス、ポジパンといったジャンルのイベントを精力的にオーガナイズしていたクラブで、実質的な拠点の存在がシーン活性化における重要な役割を果たしたのは言うに及ばず、夜な夜な黒い衣服を身に纏ったオーディエンスや関係者が集っていました。
その「黒い塊」が集まり狂乱する様は、まさにムーブメントと呼ぶに相応しい、強烈なパワーを持っていたことと思います。

ちなみに、ポジパンとは「POSITIVE PUNK=ポジティブパンク」のことです。
簡単に概要だけ説明します。
従来のパンクロックが、不況や社会へのフラストレーションを背景に、反体制とか社会への問題提起といったポリティカルなテーマを持っていたこと、またその破壊的なパフォーマンスなどから、「ネガティブなもの」として、マスメディアは好意的に取り扱っていませんでした。
一方、ポストパンクから派生したニューウェーブのバンド達はというと、政治的なイデオロギーや破壊衝動ではなく、自己を表現する美意識とか、または音楽性の探求とか、そういった方向に注力していきました。
そうなると、メディアとしても題材として扱い易い、ネガティブではない、ということから「ポジティブパンク」なんていうネーミングが誕生したらしいです。
ですが、そう呼ばれるバンド達は総じて、極めて耽美的で、一様に暗い性質を持っていたことから、その音楽性や佇まいとネーミングの間にやたら距離があるな、という感じなのですが。笑
(日本にもこのポジパンのムーブメントは少しのタイムラグで入ってきました。
良いバンド沢山ありますので、今後機会があればまた書いてみようと思います。)
去年、「Rick Owens」が来日した際に東京でパーティーが行われていましたが、引き寄せられるようにブラックファッションに身を包んだファンや関係者が集う、その「黒い塊」を僕は少し距離を置いて眺め、在りし日の「BAT CAVE」の姿を想像し、その幻影を重ねてみたりしていました。
70年代初頭にロックシーンを席巻したグラムロックが内包し、発散していた世界観を「デカダン的」と表現する向きもありますが、そのベクトルはあくまで煌びやかでいかがわしく、享楽的且つ刹那的なものでした。
そう、刹那的なその様が、デカダンス=退廃的、と解釈されるのは大いに理解できますが、グラムロックの時代は、その名の通り「GLAMOROUS」にウェイトが偏っていました。
その後、80年代初頭のロンドン「BAT CAVE」。
コウモリの巣穴、みたいなニュアンスでしょうか。
これまた名は体を表すといった感じで、超アングラ趣味全開。
地下室の秘事みたいないかがわしさと、蜘蛛の巣が張った空間、埃と酒とタバコと〇〇の匂い、みたいな世界観。
代表的なバンドは「SPECIMEN」ですねやっぱり。
「Kiss Kiss Bang Bang」(タイトル最高!!)、「The Beauty of Poison」あたりはマジで名曲なんで聴いてみてください。
この手の分野の音楽としては非常に聴き易い(エグみが少ない)はずです。
ただひたすらに「アングラ的デカダンス」を地で行くようなシーン、これを「ゴス」とか「ゴシックロック」と呼称するのですが、前段で書きました、この「BAT CAVE」世代の少し先輩格にあたるゴスの始祖「BAUHAUS(バンド)」が、グラム時代の名曲をカバーし、グラムロックの新たなる継承者としての認知を確立していたことで、「デカダンス」と「グラマラス」が結実した、と僕は捉えています。

大変長くなりました。
ここで話は戻って「Rick Owens」。
氏の持つ美的感覚の一端として、このようなカルチャーが存在するということは疑う余地がないはずですし、僕自身、少なからずの理解と傾倒があるからこそ、強く惹きつけられ続けているのだろうと思います。
そしてそれらのアングラ的要素のみに終始することなく、ラグジュアリーで洗練された佇まいと、ストリートカルチャーの匂いまでもミックスして創り上げられたブランド像故に、極マイノリティ層のフェチズムを満たすだけでなく、マジョリティ層の欲求にまで訴求し得る強さを獲得している、という事実があります。
「相反する要素を掛け合わせた時に見たことのない美しさと新たな価値が生まれる。」
これはまさに真理だな、とつくづく思います。
好む好まざるを超えて、服飾と文化には切っても切り離せない関係性があります。
「好きが高じて」という言葉がありますが、その基点を探るという行為も楽しいものです。
あくまで主観で充分だと思います。
そのような知識経験の蓄積が、自身の持つアイデンティティと融合した時、それが衣服を身に纏うという行為を「スタイル」へと昇華するファクターと成り得るのではないでしょうか。
そんな話でした。
いやー、自由気ままに書き散らかしていると本当延々と続いてしまいそうなんで、ここらで終わりにします。
久々の「inside of thought.」、個人的には非常に楽しく書き終えました。
ここから暫くは、prasthana sendagaya storeのBGMが、ゴス/ポジパンプレイリストになりそうなのは言うまでもないです。
一応最後に、
AW大変充実していますので、是非お出かけくださいね。
それでは
宜しくお願い致します。