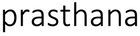inside of thought.#6 【私的名盤解説邦楽篇①】
prasthana co., ltd. 代表/デザイナーの武井です。
春
否
日によっては初夏の陽気。
ふと気付けば4月末になっていました。
世はGW、この時期って毎年まぁそんな気候ですよね。
我が旗艦店 prasthana sendagaya storeにはドライ複数の他に3種類の植物達がおりまして、そのうちの1種、アデニウム(通称アデ)がダントツで季節毎に豊かな表情を見せてくれます。
冬の入口くらいに全ての葉っぱが落ちた後、暫く沈黙を続けるこの植物。
毎年この時期になると黄緑色の新芽が出てくるのですが、これがですね、まぁ可愛い笑
日々伸張する様をパシャパシャ撮影してしまうほど。
温度管理がわりと難しい種と聞いていたのですが、自店の環境にしっかり順応してくれているようです。
良かった良かった、と今年も思っています。
そんなSS25期中。


というか、4月末。
前回の記事を遡ってみると、2月の前半にSS25立ち上がりのことを書いていました。
ということは、このJOURNALを放置して早2ヶ月強。
いやー、、今回ばかりは随分と間が空いてしまいました。
相変わらずこの間も様々活動はしていて、言ってしまえばまぁ、忙しめの時期ではありました。
SS(今シーズン)の量産→出荷とか、AW(来シーズン)の企画→サンプル作成とか、そして展示会開催とか。
とは言っても、バタバタと忙しなくタスクをこなすのなんて、なんならデフォルトの状態で10年やってきてますから、年に2回のこのタイミングのバタバタ、は勝手知ったるもの、であるはずなのですが、、、。
実を言うと、この間に書いていた記事があるにはあったのですが、なんかわかんないけど筆が進まず、結局未完、当該記事は現在下書きとして保存されたままになっています。
こんなこともこれまでになかったことです。
なんですかね、忙しいのはずっと忙しいんですが、その質が多少なり変容しているのか、兎に角余裕無く、目の前の仕事を粛々と遂行していくのでわりといっぱいいいっぱい、みたいな感じでした。
仕事に時間的な優先順位は勿論あれど、優劣という概念は僕の中にはなくて、このJOURNALを更新する、という仕事も自分にとっては他と同じように大切にしていることだったりするのですが、如何せん言葉のアウトプットとなると、心身、特に心に余裕がないとなかなか上手く進んでいかないものでした、僕の場合。
けどまぁ、こうしてまたつらつらと書き始めてみています。
4月末、漸く少しだけ落ち着いてきました。
まだまだAW25展示会に纏わるイベント事は続いていくのですが、ちょっと一旦一息ついて、久々更新のJOURNALで久々のテーマ「inside of thought.」になります。
「inside of thought .」=「思考の内側」と題した本記事は、このJOURNAL内における所謂雑記的な位置付け。
普段、衣服に纏わる事業を営んでいるわけですが、本業であるアパレル領域から離れて、その時々の気分で題材を定め、好き勝手に書き散らかすという、大変無責任なコンテンツとなります。
読み手によっては全くフィットしない可能性も多分に孕んでいるのは百も承知。
ですが、思考とクリエイティブの間には緊密な相互関係があるものです。
自身の立ち居振る舞いはもとより、prasthanaの創作においても少なくない影響を受けてきた様々な事象をご紹介することで、もしかしたら僕が提案している様々をご覧頂く際の解像度の向上に少し貢献できる。
かもしれません。
そんなモチベーションでやっていこうと思います。
タイトルにもありますが、僕が辿ってきた音楽遍歴について。
そして今回は日本の音楽、更に言うと、僕がカルチャーにのめり込んだ最初期の話と、少年時代にどハマりした「HR/HM」という分野にフォーカスして、私的名盤解説をやってみようと思います。
あ、一応注釈で、HR=ハードロック、HM=ヘビーメタル、です。ちなみにこれは、今はもう死語の可能性があります。笑
既にこの時点で誰に刺さるかマジで分からないのですが、それを言い出したらキリないので話を進めます。
そもそも音楽って僕にとって非常に重要なものです。
美的な感覚とか、アティチュードとか、様々なものを測る指針の礎を築いてもらった、と思っています。
度々発信してきていることではありますが、少年時代の僕は、衣服をはじめその他諸々の様々な文化の中で、何よりも先に音楽に夢中になったタイプでした。
きっかけなんていつも唐突なものです。
記憶に残る、その後の人生のターニングポイントに成り得る(成り得た)ような出会いって、誰しも生涯の中で幾度か経験するものだと思いますが、中学2年の僕に、それは突然訪れました。
よく遊びに行っていた友達の家、にいた兄貴。
彼は当時19とか20歳だったと思いますが、ESPという音楽の専門学校に通われていて、所謂ギターキッズを地で行くような人でした。
当時は、耳障りの良いメインストリームのポップスの他に、ビジュアル系と呼ばれるようなアーティストが地上波とかにもガンガン出始めていたタイミングで、マスのレベルでも得られる情報が増えてきていた時代でした。
その様からなんとなく「ロック的な何か」をぼんやりと感じ取ってはいたものの、そんな薄っすらとした興味を持っていたに過ぎなかった武井少年(当時バスケ部所属)に、その兄貴は語りかけます。
「ライトハンド(奏法)って知ってるか?」
アメリカのレジェンドバンド「Van Halen」のギタリスト、エドワード・ヴァン・ヘイレンが編み出した、否正確に言うと、それにフォーカスして広く世に知らしめた「ライトハンド奏法」とは、指板を右手の人差し指もしくは中指でタッピングして音を鳴らす、というもの。
ギターの演奏って、左手で指板の然るべきポジションを押さえて、右手でピッキングして音を出す、というのが基本的なスタイルなので、ちょっとした特殊奏法、という感じ。
少し専門的になりますが、ハンマリングオンとプリングオフを連続して行う、というのが実態です。
文章にすると「ふ〜ん、、で?」って感じかもしれませんが、これがですね、実際に目にして音を聴くと、まぁ、トリッキーな感覚を得ます。
断続的に細かく音が連なるのですが、ピッキングのアタックが無い分、なんというか非常にレガート(滑らか)なニュアンスで、例えるなら電子音みたいな感じ?ちょっと違うけど、兎に角、14歳の少年にmassiveな衝撃を与えるには充分でした。
それからというもの、友達の家に行っては兄貴の部屋に入り浸るようになり、様々な知見を得ました。
領域で言うと先述したビジュアル系〜HR/HM(ハードロック/ヘビーメタル)界隈が兄貴の得意分野だったこともあり、その手の情報をそれこそスポンジのように吸収する中学2年生。
「学校の先生がLUNA SEAのSUGIZOさんのギターテックとしてツアーを回っているんだけど、最早楽器というより精密機械のようなセットだって言ってた!」
とか。
※注釈:当時LUNA SEAの弦楽器隊御三方はESPとエンドース契約していました。
「D.T.Rのトモさんはプライベートでもアメリカンのいかついバイクに乗ってて、一回学校に来た時に喋ったことあるけど良い人だった!」
とかとか。
※注釈:D.T.RはX(X JAPAN)の黎明期〜メジャー初期に在籍していたベーシスト沢田泰司氏が率いたバンド。
ちなみに、もう一人のギタリスト藤本泰司氏は、JUDY AND MARY結成時のオリジナルメンバーだったりします。
「マジすか!?すげー!」みたいなリアクションを毎度していたと記憶しています。
この当時の日々は、間違いなく僕が音楽に自覚的に接し、相対した最初であり、それと同時にカルチャーにのめり込むようになる入口でもありました。
なんというか、自分の中でパズルのピースがバチん!とはまったような感覚を得て、「自分にはこれしかない」といった勢いで猛烈にギターを弾き始めるわけなのですが、今振り返ってみても、それはもう良質な影響源がめちゃ沢山あったな、と思います。
兄貴が教えてくれるアーティスト群は、その筋の基本といったような、押さえておくべき必須の人達から、少々マニアックな部分まで多岐に渡り、全てを網羅するには僕自身の受け皿的に色々と足りなかったので、かいつまんで自分の感性にフィットするお気に入りを見つけては真似してギターを弾いてみる、みたいなことを延々と繰り返す、そのような時間を過ごしました。
その後高校に進学してからは、部活動はせずアルバイトと校外での音楽活動に命を燃やす笑、ようになるのですが、それはまた別の話。
ーーーーーーーーーー
さてここから本題です。
そんなふうにして音楽と密に接し、気になるアーティストを見つけると、それを基点に掘り下げ掘り下げ、、、芋蔓式に本当にたくさんの作品を聴いてきました。
それは今だに趣味として、ファッションと同じように愛してやまない行為です。
自分の進むベクトルに大いなる影響を受けた、私的名盤に堂々と名を連ねる作品群をご紹介していきます。
私的名盤解説邦楽篇①
この時期に接した作品で、まず最も大きな影響を受けたのは、間違いなくこれですね。

artist:LOUDNESS album:LOUDNESS
日本を代表するHR/HMの分野におけるレジェンドバンド「LOUDNESS」第3期唯一のスタジオ音源(1992年作)
その活動歴の長さに加えてメンバーチェンジも頻繁に行われている事情故に、時期によってかなり音楽性とか雰囲気に違いがありまして、誰がどのような視点で語るかによってその評価は大きく変わるものと思いますが、まぁ一般的にも名盤と呼んで異論はないでしょう、という一枚。
ジャケットデザインは美術家、横尾忠則氏によるもの。これだけでもかなりの文化的価値があるのではないか、と思います。
ちなみに、純粋にLOUDNESSの前身、というわけではないのですが、ギタリスト高崎晃氏とドラマー樋口宗孝氏は、LOUDNESS結成以前にLAZYというバンドで既に一度デビューを経験されていて、そのLAZYのヴォーカリストは影山ヒロノブ氏。
影山氏は後にアニメのドラゴンボールの主題歌(CHA-LA HEAD-CHA-LA)によって一般的にも広く認知された方です。
で、この作品。
これがですね、非常に強烈な内容。
端的に表現すると、90年代初頭、当時の世界的な潮流だった(この辺の詳細は今回は端折ります)空気感をモロに反映させたグルーヴィーなメタルサウンド。
この頃のメンバーのビジュアルもかなり強烈で笑、80年代まで脈々と受け継がれてきた、この手のジャンルが持っていた様式美をことごとく打ち壊すかのような、なんとも男臭い仕上がり。
そして更に、この第3期LOUDNESSには人々を惹きつける強烈なフックがありました。
というのも、このタイミングで他2人のオリジナルメンバーより、少し若手世代のプレイヤーがヴォーカルとベースのポジションに加入しているのですが、それが山田雅樹氏、沢田泰司氏、なんですよ。
ピンとこないかもしれませんが、山田雅樹氏はFLATBACKER〜EZOを経て、沢田泰司氏はXを経てのLOUDNESS参加。
EZOは全米デビューも果たした北海道出身のバンドで、KISSのジーン・シモンズがプロデュースしたことでも著名。(僕は改名前のFLATBACKERが特に超好きです)
KISSは、かのRick Owens御大もリスペクトを表明しているような、アメリカにおける国民的なアーティストですね。
そしてX。
XってあのXですよ、X JAPAN。
「XのTAIJIがLOUDNESSに加入、!!」って、残念ながら僕はリアルタイムでこの作品に触れていたわけではないので、後追いでは計り知れない、その当時はけっこうな衝撃だったのではないか、、と思います。
そんなトピックも相まって、この頃のLOUDNESSはセールスやライブ動員が飛躍的に伸び、そして更に女性層にもコミットしていた笑、と言う奇跡の現象が起こっていたと伝え聞いています。
オリコン最高順位2位らしいですよ、今調べたら。
僕はギターを弾き出したかなり最初期にこの作品、ならびにギタリスト高崎晃氏のプレイに触れたのもあって、自身の技術レベルはその限りではないですが、音楽を観る目、じゃないか、聴く耳は物凄い肥えていたと自認しています。
その後、邦楽洋楽問わず様々な作品を聴き漁る過程においても、この作品がベースにあるが故に、特にテクニック的な部分では驚くようなことが極めて少なかったです。
全音楽ファン必聴!!
とは間違っても言えませんが、僕は非常に大きな影響を受けた作品ですね。
MVにもなっている「BLACK WIDOW」、他には「SLAUGHTER HOUSE」、「PRAY FOR THE DEAD」辺りから是非。
さぁどんどんいきましょう。
2枚目はこちら!

artist:DEAD END album:ZERO
稀代のカリスマヴォーカリストMORRIE氏率いるDEAD ENDの解散前最後のスタジオ音源(1989年作)
この作品と前作shambaraで迷ったのですが、1枚選ぶならこれでしょ!! ということでこちら。
DEAD ENDってその音楽性は勿論、ビジュアルや佇まいなど何処を切り取っても異質、というか、孤高、というか、、非常に独自性とカリスマ性に溢れるバンド。
メタルというカテゴライズで語られることが多いにも関わらず、その後ビジュアル系として発展していくシーンにも多大すぎる影響を及ぼしました。
そのイメージを牽引していたのは、ヴォーカリストであるMORRIE氏の醸し出す雰囲気によるところが大きいのですが、兎に角全方位的に、トータルでカッコ良いです。
今だプロアマ問わず、氏の心奉者は数え出すと枚挙にいとまがない。
ちなみにジャケット左上の人物がMORRIE氏。イケメン、とかそういうのを超越して神ですもはや。
80年代から盛り上がりを見せたJAPANESE METAL 通称ジャパメタのムーブメントから出てきたDEAD END。
活動初期は所謂メタル的な音像にピッチ高めの個性的なヴォーカルが乗る、そして歌詞はおどろおどろしいエログロ路線という、それはそれで非常に独特なスタイルでしたが、作品を重ねる毎に徐々にメタル的な要素が薄れ、歌詞世界も神秘性を増していき、本作ZEROにおいては全くメタルではないと言い切ってしまえるような内容となっています。
この作品、曲調的には(一部例外あれど)全編を通して基本的には明るい、影というよりは光、といったニュアンスの楽曲群を主として構成されていますが、MORRIE氏による歌詞を注意深く聴いてみると、終末思想的な世界観を表現した壮大なコンセプトアルバム、という見方もできると僕は捉えています。
サイバーパンクなんかにも通ずる、個人的に大好物な世界観。
他のメンバーも技術レベルが凄まじく高くて、特にドラマーのMINATO氏はDEAD END解散後、スタジオミュージシャンとして様々な分野で大活躍されます。
TRFとか福山雅治とか氷室京介(!)とか、MINATO氏のドラムを意識せずに聴いている可能性って実はかなり高かったりします。
鉄壁と言えるリズムセクションの上に、空間を揺蕩うような超個性的なギターのフレーズと、ある種狂気性を帯びた、耽美/デカダン文学のような言葉が紡がれていく、という独自すぎるスタイルを確立した本作。
僕はprasthanaでの活動においても、言葉の使い方/選び方にはかなり繊細に気を遣っていまして、そんな思考の多くの領域を占める要素が、MORRIE氏から受けた影響だったりします。
まずは四の五の言わず「SERAFINE」、次いで「I'M IN A COMA」が個人的にはお勧め。
はい、次!

artist:MORRIE album:ロマンティックな、余りにロマンティックな
2枚目に挙げたDEAD ENDのカリスマ:MORRIE氏のソロ作品2枚目(1992年作)
改めてカッコ良い。かなり久し振りにまじまじとジャケットを見ましたが、その御尊顔たるや、、って感じですね。
1990年のDEAD END解散後、ソロとしてのキャリアをスタートさせたMORRIE氏。
1995年に自身のソロ3枚目にあたる「影の饗宴」という作品をリリースした後、長い沈黙に入ることになりますので、この間の5年間が氏のソロ活動の第1期と言えると思います。
第1期中の3枚の作品はマジでどれも素晴らしいのですが、ここでもやはり1枚選びましょう、ということならば、これですね。
タイトルはドイツの思想家、フリードリヒ・ニーチェの著作「人間的な、あまりに人間的な」からの引用です。
アーティストに限った話ではなく、知的な雰囲気を纏った人っていますよね。
なんかちょっとミステリアスで、更には神経質そうで、、だけど不思議と興味を惹かれる、みたいな人。
MORRIE氏ってそれの最たるもの、知的な雰囲気、なんて生半可なものではなく、あからさまに知的。
音楽性もそうですが、その歌詞にも色濃く氏が持つ世界観が反映されていて、決して一般大衆的なものではないですが、ある種のキャッチーさと独自の美意識が超高次元で融合した作品が本作です。
DEAD END時代から際立っていた歌詞世界も、ここへきて更に孤高の高みへと昇り詰めているような印象で、文学的、そして哲学的な、比喩に比喩を重ねたような難解な表現も多いのですが、掛け値なしに素晴らしいです。
音像としてはフリージャズ、AOR、インダストリアル、ニューウェーブなど、ロックやメタル以外にも多様な要素を飲み込んで咀嚼し、そしてMORRIE流のPOPSに昇華してアウトプットされています。
かなり効果的に随所にホーンセクションが入るのですが、これがなんともヒステリックで、ゾワゾワと神経が逆立つ感じを覚えます。
イージーリスニングの対極にあるような、きちんと向き合って聴かなければ、その真価には到底辿り着けないような音楽。
言ってしまうと聴き手を選ぶ作品だと思います。
僕は超好きです。
残念ながら本作は既に廃盤、実物を入手することが難しい状況となっていて、現状サブスク解禁もされていないようなのですが(まぁされないか、笑)、YouTubeで探すと聴けちゃったりします。
「破壊しよう!」とか「ロマンティスト狂い咲き」「あとは野となれ山となれ」辺りがまずはお勧め。
少しでもご興味あれば是非。
ーーーーーーーーーー
そろそろ疲れましたよね? 恐れ入ります。
一旦今回はこのくらいにしときます。
計3枚、これらは基本的に自分が音楽活動をしていた頃、特にその黎明時期に出会った作品達なので、我ながらかなり偏った傾向が見て取れますが、どれも現在に至るまで断続的に聴き続けている、正に私的名盤です。
あくまで僕の場合ですが、自分で事業なんてやっていると
「脇目もふらず兎に角突っ走る!」みたいなスタンスが常態化してしまうもので、そんな瞬間を積み重ねて10年、2025年の今に至ります。
日々を忙しなく、余裕なく駆け抜けているわけですが、ふと立ち止まって現状を俯瞰して見てみる、そんな余白を持つことって、様々な観点から考えて絶対的に必要なことだと思います。
音楽は記憶と結びつきやすいものです。
「昔よく聴いていたあの曲」って、その当時の情景とか自身を取り巻いていた環境、、そのような記憶とセットになっていませんか。
自分の現在の軌道を改めて確認するという行為において、自身の出自を詳らかに示してくれる私的名盤(名曲)の存在は、とても役に立つのではないか、と思っています。
綺麗に纏まったか?笑
それにしても、この手の話はマジで延々とできてしまいますね。
今回は邦楽HR/HM篇でしたが、少しでも反響があれば、調子に乗ってその他の分野についても言及する機会を設けますので、是非店頭なんかで話題を振って下さい。
次回JOURNAL更新は2ヶ月も空かないように笑
しっかりと進めていきたいと思います。
それではこの辺で。
宜しくお願い致します。